Need Help?
学部科目等履修制度ほか
最終更新日: 2025年3月10日
【5】学部科目等履修制度
文学部で開設されている諸課程履修により各種資格を取得するために、文学部開講科目を履修することが可能となる制度です。
履修許可された科目については、原則として履修辞退および登録を取り消すことができませんので、学修計画を立てて、履修申込みをするようにしてください。
1.本制度を利用して履修できる学部科目
-
◆基礎となる学科・専攻の必修科目(ただし、指定科目は文学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位修得するよう指定した科目となりますので、本制度の適用外です。)。
-
◆教員免許状取得に必要な教職課程科目・教科に関する科目・教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目(日本国憲法、情報機器の操作、体育)
-
◆社会教育主事資格、博物館学芸員資格、図書館司書資格、学校図書館司書教諭資格、本願寺派学階資格、本願寺派教師資格の課程で、資格取得に必要な必修科目
※ただし、受講を制限する科目もあります。
2.学部科目履修制度について
(1)履修申請について
学部科目履修を希望する大学院生は、下記に定める期間に所定の願書に必要事項を記入し、文学研究科長に提出し、文学研究科委員会・文学部教授会の議を経て、履修を許可します。
(2)履修制限単位数
1年間で32単位を上限とします。(ただし、指定科目の単位数は含みません。)
(3)科目等履修料について
科目等履修料(以下、「履修料」という。)は学費等納入規程において規定した金額とする(1単位7,500円)。なお、単位の計算方法は学則に準じます。
ただし、下記の科目については、科目等履修料を免除するものとします。
- 各専攻の基礎となる文学部各学科(専攻)の必修科目
- 「教職に関する科目」
- 大学院文学研究科各専攻で取得可能な専修免許状にかかる免許教科の「教科に関する科目」
※ただし、専攻ごとに指定される専修免許状の教科とは異なる中学校教諭一種免許状または高等学校一種免許状を取得するに必要な科目を履修する場合の教科に関する科目については有料とします。 - 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目のうち、「日本国憲法」「体育」「情報機器の操作」に関する科目
- 本学が教員免許状取得のうえで特に必要と定める科目
- 社会教育主事資格、博物館学芸員資格、図書館司書資格、学校図書館司書教諭資格、本願寺派学階資格、本願寺派教師資格課程に関する必修科目
(4)履修制限科目等について
- 「科目等履修生に関する要項」第4条で定める以下の科目については、履修できません。
Ⅰ.演習、実習、卒業論文
Ⅱ.語学科目等で受講者数を制限する科目
Ⅲ.その他、科目の性格上履修が認められない科目 - 情報教育科目及び「考古学実習」「文化財実習」、図書館司書資格課程の一部科目については、受講可能であっても、受講者数に制限があるため、その選考にあたっては、文学部在学生の履修登録を優先します。
- 「博物館実習」の受講については、「文学部博物館学芸員課程博物館実習内規」により取り扱うものとします。
3.学部科目履修に関する手続きについて
(1)学部科目履修申込について
- 履修申込期間
原則として、年1回(学年始)のみの申込とします。(※一部科目を除く)
詳細は、毎年度1月末以降に発表される前期オリエンテーション日程を確認してください。 - 提出書類
「大学院文学研究科・実践真宗学研究科生の学部科目履修登録申請書」 - 履修許可通知
履修登録開始日にweb登録画面上で通知します。 - 注意事項
◆予備・事前登録を必要とする科目の受講を希望する場合には、別途定められた予備・事前登録期間に必ず登録を行ってください(※文学部時間割表各授業科目1番右の備考欄に「予備・事前科目が必要」と記載のある科目)。
◆図書館司書課程科目の以下の科目については、先修制を採用している関係上、学部と同様に後期履修指導期間(9月中旬)に受け付けを行います。
授業科目 履修の要件となる授業科目および単位数 (司)情報サービス実習B (司)情報サービス論(2単位) (司)情報資源組織実習A (司)情報資源組織論(2単位) (司)情報資源組織実習B (司)情報資源組織論(2単位)
(2)学部科目の履修登録について
- 履修登録期間
履修登録については、web登録としますので、web履修登録期間に登録を完了してください。
詳細は、毎年度1月末以降に発表される前期オリエンテーション日程を確認してください。 - 履修登録方法
履修許可された科目については、web履修登録画面上で「確定」科目として表示しますので、他の文学研究科の科目とともに履修登録を行ってください。
(3)有料科目受講にかかる手続きについて
- 履修許可科目のうち、科目等履修料の納入が必要な場合は、対象者について履修登録開始日に文学部掲示板にて発表します。
- 対象者は、下記の期間に必ず定められた銀行口座に履修料を入金してください。納入期間は許可発表日から1週間です。【期間厳守】
※上記期間内に文学部教務課(大学院窓口)に納入用紙を受け取ってください。
※入金後、大学提出用控えを文学部教務課まで持参してください。
※期間内に納入できない場合、受講許可を取り消しますので、もれなく手続きを行ってください。
【6】龍谷大学大学院社会学研究科修士課程開設科目の履修方法
1.履修の認定
文学研究科修士課程の修了要件である選択科目として、社会学研究科開講科目「特論」「調査研究」の内4単位のみ、在学中に履修し、修得することができます。
社会学研究科開講科目「特論」「調査研究」の内4単位のみ、在学中に履修し、文学研究科修士課程の修了要件である選択科目に含むことができます。
2.履修可能科目
社会学研究科社会学専攻・社会福祉学専攻の「特論」および「調査研究」
3.履修手続き
指導教授(主)の了承を得た後、履修登録期間中に文学部教務課窓口へ申し出てください。修士課程社会人学生の登録料は、1単位につき、32,000円です。
【7】「京都・宗教系大学院連合」単位互換
「京都・宗教系大学院連合」は大谷大学大学院、皇學館大学大学院、高野山大学大学院、同志社大学大学院、花園大学大学院、佛教大学大学院、龍谷大学大学院が加盟しています。
京都を中心とした宗教系大学の大学院が、それぞれの宗教や宗派の特色を生かし、2006年度から単位互換を実施しています。詳細については、別に配付する「京都・宗教系大学院連合」のパンフレットを参照してください。
なお、履修した授業科目の単位は、留学による単位認定と合わせて15単位を超えない範囲で本学大学院文学研究科において履修したものとみなすことができます。(大学院学則9条第1項および第2項参照)
(1)履修登録受付期間
履修登録開始日から1週間(予定)です。詳細は、ポータルサイトにてお知らせします。
(2)履修登録方法
- 履修登録関連書類とともに配付する【「京都・宗教系大学院連合」単位互換履修出願票】に必要事項を記入してください。通年登録のため、前期開講分、後期開講分を一度に登録してください。ただし、後期での登録修正はできませんので、計画的に履修登録を行うようにしてください。
- 「京都・宗教系大学院連合」の単位互換科目履修出願にあたっては、指導教授(主)の受講認定が必要ですので、事前に指導教授(主)と履修面談のうえ、出願してください。
- 出願後、文学研究科委員会にて審議を行い、受講の可否について判定いたします。
- 学内の申し合わせにより、本学大学院実践真宗学研究科が提供する科目について受講登録することができません。
- 受講許可された科目については、webによる履修登録が不要ですので、出願票の提出・委員会での受講許可をもって、履修登録したものといたします。
(3)単位認定について
- 認定単位数
龍谷大学大学院学則第9条第2項の規定により、他大学の大学院で履修し、修得した単位と合わせて15単位を限度とする。ただし、種智院大学開講科目については、単位認定の対象としない。 - 認定する分野
【修士課程】選択科目での単位認定とし、修了要件単位数に算入する。
【博士後期課程】関連科目での単位認定とし、修了要件単位数には算入しない。 - 認定方法
認定は個別認定とし、原則として科目名は「互換大学名(講義区分)」とする。ただし、国際学研究科の単位互換科目について、内規第4条第3項に基づき、本学大学院学則で定める他研究科科目の履修として単位認定を行うものとする。 - 成績表記:素点による評価
- 認定時期:前期開講分を含め、年度末に一括して認定します。
【8】諸課程科目等の履修方法
文学部では、大きく9の資格課程が設置されているほか、文学研究科においては3種類(教職課程・公認心理師受験資格※・臨床心理士受験資格※)の資格課程が設置されています。
学部に設置されている資格課程については、「学部科目履修制度」を活用し、資格を取得することが可能です。ただし、修士課程では2年間、博士後期課程では3年間という限られた学修期間と1週間39講時という時間割の制限のもとでの資格取得であるので、複数の資格の取得を必ずしも保証することはできません。したがって、皆さんは、大学院での学修計画と大学院修了後の将来計画に応じて、取得すべき資格を選択する必要があります。
特に学問分野の異なる複数の資格の取得を目指す場合は、2年間ないし3年間、もしくはそれ以上にわたる綿密な履修計画を立てなければなりません。
教育実習や博物館実習のように、一定期間を実習に専念しなければならない科目もあるため、職業や家庭の事情等で履修が困難であると予想される場合には、それらを解決し、履修を可能とするための調整が本人の努力に求められます。学生の個々の事情に対するすべての調整を大学側に求めることはできません。学生個々の事情により履修が不可能であると最終的に判断された場合には、当然のことながら資格取得を断念しなければなりません。
大学院生における諸課程資格取得にあたっては、大学院での学修と資格取得のための科目履修との両立をはかったうえで、科目履修をしなくてはなりません。
臨床心理学専攻に限る
1.教職課程
教職課程は、教員免許状の取得を目指す学生を対象とした課程です。教科等に関する確かな専門的知識はもちろん、広く豊かな教養、人間の成長・発達への深い理解、生徒に対する教育的愛情、教育者としての使命感を基盤とした実践的な指導力を養成することを目的に設置しています。
(担当窓口)教職センター大宮学舎西黌1階
(関係情報)『教職課程ガイドブック』教職センターHP
(URL)https://www.ryukoku.ac.jp/faculty/kyoshoku
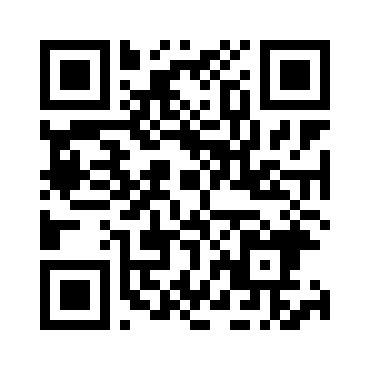
2.本願寺派教師資格課程
本願寺派教師資格課程は、浄土真宗本願寺派における寺院の住職や布教使になるために必要となる資格課程です。
この課程は、最終的には浄土真宗本願寺派が実施する本資格に関連する試験・研修を受けなければなりません。
資格制度の詳細について、不明な点等がありましたら、浄土真宗本願寺派僧侶養成部に尋ねてください。
履修に関する詳細については、担当窓口に尋ねてください。
(担当窓口)文学部教務課 大宮学舎西黌1階
(関係情報)
(URL)https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/prog.html
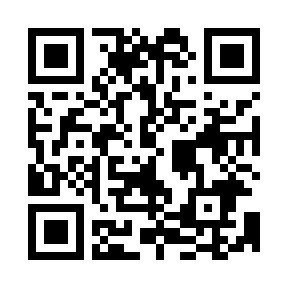
3.本願寺派学階課程
学階とは、浄土真宗本願寺派(西本願寺)における、教師(同派末寺の住職になれる僧侶)の資格のひとつです。真宗学、仏教学に通じた者に与えられる学位で、得業・助教・輔教・司教・勧学の5段階あります。
本学において、所定の科目の単位修得等の要件を満たすと学階を受けるための予試・本試が免除され、直接、殿試(初めて学階授与を願う者が受けるための試験)を受験することが可能となります。
(担当窓口)文学部教務課 (大宮学舎西黌1階)
(関係情報)
(URL)https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/prog.html
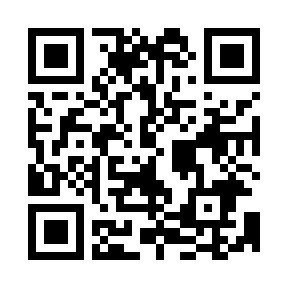
4.その他資格課程について
●学校図書館司書教諭課程
司書教諭とは、小学校・中学校・高等学校等の図書館で専門的職務に従事する教員のことをいいます。1997年の学校図書館法の改正により、2003年度から12学級以上の規模を持つすべての小中高の図書館への司書教諭の配置が義務づけられました。
司書教諭は学校司書と同じく、学校図書館における専門的職務であり、深い人間理解に基づく、豊かな読書指導を行うことはもとより、読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を開催したり、児童・生徒の学習に対して図書館の利用に関する指導を行うこと等を職務としています。
(担当窓口)文学部教務課 (大宮学舎西黌1階)
(関係情報)履修要項WEBサイト
(URL)https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/prog.html
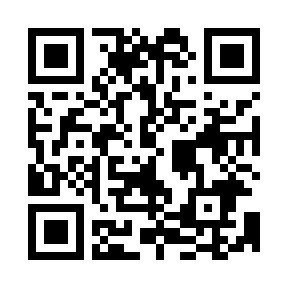
●図書館司書課程
図書館司書とは、図書館等で資料の選択、収集、整理(分類、目録)、情報サービスなどを行う専門的職員です。公共図書館、大学図書館、専門図書館、学校図書館などで働いています。
生涯学習社会といわれる現代において図書館司書が果たす役割は大きく、利用者に対して質の高いサービスを提供でき、多様なニーズに対応できる人材が求められています。また図書資料だけにとどまらず国際化・情報化の時代にふさわしく情報メディアの収集・管理、情報検索などについての自在な活用能力も求められています。
(担当窓口)文学部教務課 (大宮学舎西黌1階)
(関係情報)履修要項WEBサイト
(URL)https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/prog.html
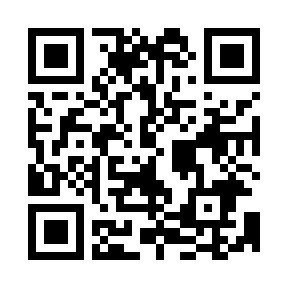
●博物館学芸員課程
資料の収集・保管・展示および調査研究等の業務に携わり、博物館の事業全般をサポートする博物館学芸員を養成します。
(担当窓口)文学部教務課 (大宮学舎西黌1階)
(関係情報)履修要項WEBサイト
(URL)https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/prog.html
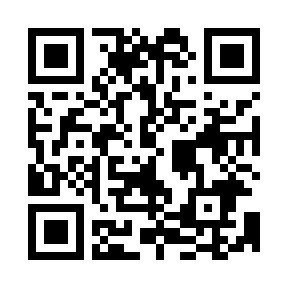
【9】学会発表援助費について
学会発表援助費とは、大学院生研究援助費の一つであり、大学院生の学修・研究活動を支援するためのものです。以下の申請方法等を、よく確認して申請してください。
また、申請時期等の詳細については、申請時期の1ヶ月前にポータルサイトでお知らせします。
1.申請資格
大学院文学研究科に在学する正規学生(修士課程・博士後期課程)
2.申請時期
具体的な申請期間については、別途ポータルサイトで周知します。
3.申請対象
以下に該当するものが申請・支給の対象となります。
- 原則として、日本学術会議協力学術研究団体等の学会が主催、共催及び協賛する大会・研究発表会とする。
- 学内開催の学会については、本学で開催される前項に定める大会・研究発表会のほか、各学科・専攻で付置する学会の大会・研究発表会とする。
- 前2項の大会・研究発表会以外の大会・研究発表会については、申請に基づき、文学研究科委員会の議を経て、対象とする場合がある
4.申請方法
以下の手続にて、申請すること。
- 文学部教務課で配付する「文学研究科 大学院学会発表援助費 支給申請書」に必要事項を記入し、指導教授に所見記入・認印を押印してもらう。
- ①指導教授の承認を経た「支給申請書」、②学会の概要がわかる書類、③申請する学会発表のプログラム等を添付し、文学部教務課へ提出する。
5.申請回数
申請回数については、1人につき年3件を上限とする。ただし、同一の大会・研究発表会で複数発表する場合については、1件としてカウントする。グループ発表については、発表者(代表者)1名が申請対象とし、1件としてカウントする。
6.支給額
個人発表の場合は、学会発表1件につき10,000円を支給する。また、※グループでの発表の場合も、人数にかかわらず学会発表1件につき10,000円を支給する。
7.支給方法
研究科委員会で支給の可否を審議。承認された申請者に対して、申請された銀行口座に振り込みます。
8.その他注意点
- 「支給申請書」1枚につき、学会発表1件を記入してください。
- 代理での提出は認めません。
- 学会の概要がわかる書類、申請する学会発表のプログラムが外国語で書かれている場合は、必ず日本語訳を添付してください。
※グループでの発表:
1演題について複数の演者が登壇した場合は、1グループとみなします。
【10】研究生・特別専攻生制度
1.研究生制度
本学大学院博士後期課程に3年以上在学し退学した方で、更に本学大学院において博士論文作成のために研究の継続を希望する方を対象とした研究生制度があります。研究生の取り扱いについては、「研究生要項」(大学院学則第9章の2 研究生の項を抜粋)を確認してください。
研究生の申請については、下記の要領で受け付けます。
(1)願書受付期間
1月中旬~2月末日(予定)
(2)願書提出先
大宮学舎文学部教務課
(3)出願書類
- 研究生願書 1通(本研究科所定のもの、写真1枚添付)
- 研究生願書調査書 1通(本研究科所定のもの)
- 研究生証交付願 1通(本研究科所定のもの、写真1枚添付)
- 研究計画書(400字詰原稿用紙5枚程度、様式自由、指導教授と相談のこと)1部
(4)待遇
-
○指導教授による指導を受けること。
-
○大学院学生の研究を妨げない範囲で、科目の聴講を許可します。ただし、科目履修による単位認定は行いません。
-
○大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用することが可能です。
(5)研修費
年間2万円(※受入許可後、年度初めに入金していただきます。)
- 申請に関する詳細は、12月中旬(予定)にポータルサイト等でお知らせします。
2.特別専攻生制度
本学大学院文学研究科修士課程修了者、本学大学院文学研究科博士後期課程修了者(博士論文を提出し、博士の学位を授与された者)で、更に本学大学院において研究の継続を希望する方を対象とした特別専攻生制度があります。特別専攻生の取り扱いについては、「特別専攻生規程」を確認してください。特別専攻生の申請については、下記の要領で受け付けます。
(1)願書受付期間
1月中旬~2月末日(予定)
(2)願書提出先
大宮学舎文学部教務課
(3)出願書類
- 特別専攻生願書 1通(本研究科所定のもの、写真1枚添付)
- 特別専攻生願書調査書 1通(本研究科所定のもの)
- 特別専攻生証交付願 1通(本研究科所定のもの、写真1枚添付)
- 研究計画書(400字詰原稿用紙5枚程度、様式自由、指導教授と相談のこと)1部
(4)待遇
-
○指導教授による指導を受けること。
-
○大学院学生の研究を妨げない範囲で、科目の聴講を許可します。ただし、科目履修による単位認定は行いません。
-
○大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用することが可能です。
(5)研修費
年間2万円(※受入許可後、年度初めに入金していただきます。)
- 申請に関する詳細は、12月中旬(予定)にポータルサイト等でお知らせします。
【11】長期履修制度について
文学研究科では、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することができる「長期履修学生制度」を、2014(平成26)年度入学生から導入しました。
詳細は、本学ホームページ(https://www.ryukoku.ac.jp/)で必ず確認してください。
1.長期履修学生制度の概要
(1)長期履修学生の定義
職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり、計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する者で、研究科委員会の議を経て研究科長が認めた者
(2)対象となる課程
修士課程・博士後期課程
(3)対象となる者
長期履修学生となることを希望する者は、本学大学院研究科に入学する者又は在学生(修了年次の者を除く)で、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する者とします。ただし、外国人留学生は、対象としません。
1)職業を有している者
2)家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
3)その他当該研究科が相当な事情があると認めた者
(4)長期履修期間
長期履修期間は年度を単位とし、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができます。ただし、休学期間は算入しません。
2.長期履修学生の申請について
(1)申請期間
長期履修は、次のいずれかの期間に申請できるものとします。
1)入学前の申請(入学手続期間)
2)入学後の申請(長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までとし、修了年度の申請を除く)
(2)申請手続
長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、以下の書類を文学部教務課に提出してください。
①長期履修申請書
②対象者であることを確認できる書類
③その他当該研究科長が必要と認める書類
長期履修申請書提出にあたっては、指導予定教員等(指導教員)の面談を受け、申請書に指導教授の所見・署名・捺印を受けなければなりません。
3.長期履修学生の許可について
申請書類に基づき、文学研究科教務委員会において審査を行い、文学研究科委員会の議を経て、許可します。
4.履修期間の変更について
長期履修学生が、許可された履修期間を事情により変更(短縮又は延長)を希望する場合は、以下の書類を文学部教務課に提出してください。長期履修期間変更申請書提出にあたっては、提出者は、指導教員の面談を受け、申請書に指導教授の所見・署名・捺印を受ける必要があります。
(1)手続き方法
履修期間を変更する場合は,学年開始の1ヶ月前までに,以下の書類を文学部教務課に提出してください。
①長期履修期間変更申請書
②その他当該研究科長が必要と認める書類
(2)変更可能回数および期間の変更
①長期履修期間の変更
在学する課程において、いずれか1回に限り認めるものとします。
②長期履修期間の短縮
標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までとします。
③長期履修期間の延長
延長については、修士課程、博士後期課程ともに長期履修期間の上限となる6年を限度とします。申請は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとします。
5.長期履修学生の学費
長期履修学生は、通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。
- 学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので、毎年度所定の費用を納入する必要があります。
【12】龍谷大学大学院文学研究科紀要
『龍谷大学大学院文学研究科紀要』への研究論文等の投稿について
大学院生の研究成果を発表する機関誌として、毎年『龍谷大学大学院文学研究科紀要』を刊行しています。研究論文等の投稿を希望する者は、次の要領で提出してください。
1.応募資格
(1)博士後期課程在学者、研究生、満期依願退学者(退学後3年以内の者)。ただし、あらかじめ所属する専攻(満期依願退学者については在籍中に所属していた専攻)の承認を得ること。
(2)修士論文提出者で所属する専攻の推薦を得た者。
2.執筆要項
(1)論文の種類は、研究論文、翻訳、研究ノートとする。ただし、翻訳、研究ノートについては、編集委員会で掲載本数を制限することがあるので注意すること。
(2)原稿量は、以下のとおりとする。
研究ノート:16,000字以内。
欧文(梵巴蔵文を含む):全体で10,000words以内。
*原稿制限文字数には、図、表も含める。
*参考文献、引用、註は、原則として、原稿の末尾に掲載する。
横書きの場合は、脚註も可とする。
(3)原稿は、Word形式のA4サイズ1頁1,000字(縦書きの場合は縦40字×横25行、横書きの場合は横40字×縦25行)の設定で印刷すること。欧文(梵巴蔵文を含む)原稿は、A4サイズで1頁あたり33行とする。
(4)原稿は、必ず綴じて提出すること。(クリップ可)
3.原稿の掲載
原稿の掲載の可否については、編集委員会の査読によって決定する。
4.応募手続きなど
(1)編集委員会事務局(世界仏教文化研究センター事務部)に設置してある文学研究科所定の応募用紙にて応募すること。応募にあたっては、必ず専攻の承認を得ること。
①研究論文、翻訳、研究ノート
応募期限:毎年度1月末日
提出先:編集委員会事務局(世界仏教文化研究センター事務部)
②修士論文に基づく研究論文
応募期限:毎年度2月末日
提出先:編集委員会事務局(世界仏教文化研究センター事務部)
(2)毎年3月中旬に、編集委員会で投稿の可否を決定し、応募者全員に通知する。
(3)原稿提出期限
提出先:編集委員会事務局(世界仏教文化研究センター事務部)
(4)応募日程の詳細については毎年12月頃にポータルサイトで周知します。
5.その他
本研究科の研究成果の公開方法として、国立情報学研究所を通じて電子化を実施する。掲載された論文等(書籍情報、画像情報、本文)の著作権(著作財産権、copyright)は個人に帰属するが、電子化し公共の利用に供する場合、掲載された論文の複製権(注1)、及び公衆送信権(注2)の行使を本編集委員会に許諾することとする。
注1 複製権:著作物を有形化し、再製することに関する権利
注2 公衆送信権:著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利
 検索
検索