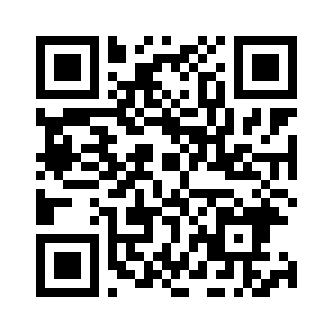Need Help?
諸課程
最終更新日: 2025年3月31日
【1】社会調査士資格
本学部総合社会学科は、社会調査の立案・計画・実施・分析・結果報告にまで至る総合的な力を習得し、官庁や企業において社会調査活動を担うことができ、その調査結果をふまえて政策や戦略を打ち出す能力を有する人材の養成に取り組んでいます。
そこで本学科では、一般社団法人社会調査協会「社会調査士」資格取得の課程を設置しています。以下の科目を履修し単位を修得した学生は資格認定申請を行うことができます。(「一般社団法人社会調査協会」サイトを参照してください)
手続きの詳細等については、その都度掲示板等にて連絡します。なお、2年次・3年次に「社会調査士(キャンディデイト)」の認定を受け、卒業時に「社会調査士」の資格を取得する場合の認定手数料は、合計で22,000円※となります。「社会調査士(キャンディデイト)」を取得せず、卒業時に「社会調査士」の認定申請を行う場合は16,500円※が必要となります。
※2023年度以降、「社会調査士」資格の認定手数料に対して社会学科実習費より補助が出ます。手続きの詳細等については、その都度教務課よりお知らせします。
(※2024年12月現在)
| 授業科目名 | セメスター | 履修条件 (協会の規定) |
履修条件 (本学部の規定) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | 社会調査入門 | 1 | 必修 | 必修 |
| B | 量的調査法 | 3 | 必修 | 必修 |
| C | 社会統計学Ⅰ | 2 | 必修 | 必修 |
| D | 社会統計学Ⅱ | 3 | 必修 | 必修 |
| E | 多変量解析 | 4 | Fとの選択必修 | 推奨 |
| F | 質的調査法 | 4 | Eとの選択必修 | 必修 |
|
G |
社会共生実習A | 5 | 必修 | 必修 |
| 社会共生実習B | 6 | 必修 | 必修 |
(注意)
- 一般社団法人社会調査協会「社会調査士」資格認定は、「E・Fのうち、いずれか1科目必修」となっていますが、本学部では「質的調査法」は必修であり、「多変量解析」についても受講を推奨します。
- 「社会共生実習A」「社会共生実習B」については、「社会調査実習」のクラスを選択してください。
【2】社会福祉士国家試験受験資格
総合社会学科では、社会福祉士の国家試験を受験できる資格を取得することができます。
1)社会福祉士の職務
社会福祉士は、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、身体上、精神上の障害や環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供するとともに、医師や保健医療サービス提供者、その他関係者との連絡および調整その他援助を行うことを職務とします。
2)社会福祉士資格の取得
社会福祉士になるためには、以下が必要となります。
- 厚生労働省令に定める社会福祉に関する科目(以下「社会福祉士指定科目」)の単位を修めて卒業すること【国家試験受験資格】
- 社会福祉士国家試験に合格し、指定登録機関において社会福祉士登録簿に登録を受けること
3)指定科目
【表1】のとおり社会福祉士指定科目に対応しています。
なお、ソーシャルワーク実習Ⅰ等の科目に先修制を設けているので、計画的な履修を進めてください
【表1】社会福祉士指定科目と総合社会学科開講科目の対照表
| 指定科目等の名称 | 総合社会学科開講科目の名称 | セメ | 単位数 | 履修条件 |
|---|---|---|---|---|
| 医学概論 | 医学概論 | 4 | 2 |
必修 |
| 心理学と心理的支援 | 心理学と心理的支援 | 4 | 2 | |
| 社会学と社会システム | 社会学概論 | 2 | 2 | |
| 社会福祉の原理と政策 | 社会福祉原論 | 3 | 4 | |
| 社会福祉調査の基礎 | 社会福祉調査の基礎 | 4 | 2 | |
| ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワークの基盤と専門職 | 3 | 2 | |
| ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 4 | 2 | |
| ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワークの理論と方法 | 4 | 4 | |
| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 5 | 4 | |
| 地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉論 | 4 | 4 | |
| 福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの組織と経営 | 5 | 2 | |
| 社会保障 | 社会保障論 | 3 | 4 | |
| 高齢者福祉 | 高齢者福祉論 | 3 | 2 | |
| 障害者福祉 | 障害者福祉論 | 3 | 2 | |
| 児童・家庭福祉 | 児童福祉論 | 3 | 2 | |
| 貧困に対する支援 | 貧困に対する支援 | 4 | 2 | |
| 保健医療と福祉 | 保健医療と福祉 | 5 | 2 | |
| 権利擁護を支える法制度 | 権利擁護を支える法制度 | 5 | 2 | |
| 刑事司法と福祉 | 刑事司法と福祉 | 3 | 2 | |
| ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 4 | 2 | |
|
ソーシャルワーク演習(専門) |
ソーシャルワーク演習Ⅱ | 5 | 4 | |
| ソーシャルワーク演習Ⅲ | 7 | 4 | ||
|
ソーシャルワーク実習指導 |
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 5 | 2 | |
| ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 6 | 2 | ||
| ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | 7 | 2 | ||
|
ソーシャルワーク実習 |
ソーシャルワーク実習Ⅰ | 6 | 6 | |
| ソーシャルワーク実習Ⅱ | 7 | 2 |
【表2】社会福祉士国家試験受験資格に関する実習演習科目の時間数と履修方法
本表は、学則別表15に基づき、社会福祉士国家試験受験資格に関する実習演習科目の時間数と履修方法について定める。
| 科目名 | 時間数 | 履修方法 |
|---|---|---|
| ソーシャルワーク演習Ⅰ | 30時間 | 演習 |
| ソーシャルワーク演習Ⅱ | 60時間 | 演習 |
| ソーシャルワーク演習Ⅲ | 60時間 | 演習 |
| ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 30時間 | 演習 |
| ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 30時間 | 演習 |
| ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | 30時間 | 演習 |
| ソーシャルワーク実習Ⅰ | 180時間 | 実習 |
| ソーシャルワーク実習Ⅱ | 60時間 | 実習 |
【3】精神保健福祉士国家試験受験資格
総合社会学科では、精神保健福祉士の国家試験を受験する資格を取得することができます。
1)精神保健福祉士の職務
精神保健福祉士は、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識および知識をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、または精神障害者の社会復帰の促進を図るための施設を利用する者の地域相談支援の利用に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを職務とします。
2)精神保健福祉士資格の取得
精神保健福祉士になるためには、以下が必要となります。
- 現代福祉学科において、厚生労働省令に定める精神障害者の保険及び福祉に関する科目(以下「精神保健福祉士指定科目」)の単位を修めて卒業すること【国家試験受験資格】
- 精神保健福祉士国家試験に合格し、指定登録機関において精神保健福祉士登録簿に登録を受けること
3)指定科目
総合社会学科開講科目は【表3】のとおり精神保健福祉士指定科目に対応します。
【表3】精神保健福祉士指定科目と総合社会学科開講科目の対照表
| 指定科目等の名称 | 総合社会学科開講科目の名称 | セメ | 単位数 | 履修条件 |
|---|---|---|---|---|
| 医学概論 | 医学概論 | 4 | 2 |
必修 |
| 心理学と心理的支援 | 心理学と心理的支援 | 4 | 2 | |
| 社会学と社会システム | 社会学概論 | 2 | 2 | |
| 社会福祉の原理と政策 | 社会福祉原論 | 3 | 4 | |
| 地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉論 | 4 | 4 | |
| 社会保障 | 社会保障論 | 3 | 4 | |
| 障害者福祉 | 障害者福祉論 | 3 | 2 | |
| 権利擁護を支える法制度 | 権利擁護を支える法制度 | 5 | 2 | |
| 刑事司法と福祉 | 刑事司法と福祉 | 3 | 2 | |
| 社会福祉調査の基礎 | 社会福祉調査の基礎 | 4 | 2 | |
| 精神医学と精神医療 | 精神医学と精神医療 | 3 | 4 | |
| 現代の精神保健の課題と支援 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ | 3 | 2 | |
| 現代の精神保健の課題と支援Ⅱ | 4 | 2 | ||
| ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワークの基盤と専門職 | 3 | 2 | |
| 精神保健福祉の原理 | 精神保健福祉の原理 | 4 | 4 | |
| ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワークの理論と方法 | 4 | 4 | |
| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 精神保健福祉援助技術論 | 5 | 4 | |
| 精神障害リハビリテーション論 | 精神障害リハビリテーション論 | 5 | 4 | |
| 精神保健福祉制度論 | 精神保健福祉制度論 | 4 | 2 | |
| ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 4 | 2 | |
|
ソーシャルワーク演習(専門) |
精神保健福祉援助演習Ⅰ | 5 | 2 | |
| 精神保健福祉援助演習Ⅱ | 6 | 4 | ||
|
ソーシャルワーク実習指導 |
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 5 | 4 | |
| 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | 6 | 2 | ||
| ソーシャルワーク実習 | 精神保健福祉援助実習 | 6 | 6 |
【表4】精神保健福祉士国家資格受験資格に関する実習演習科目の時間数と履修方法
本表は、学則別表16に基づき、精神保健福祉士国家試験受験資格に関する実習演習科目の時間数と履修方法について定める。
| 科目名 | 時間数 | 履修方法 |
|---|---|---|
| ソーシャルワーク演習Ⅰ | 30 | 演習 |
| 精神保健福祉援助演習Ⅰ | 30 | 演習 |
| 精神保健福祉援助演習Ⅱ | 60 | 演習 |
| 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 60 | 演習 |
| 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | 30 | 演習 |
| 精神保健福祉援助実習 | 210 | 実習 |
【4】社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格は、都道府県、市町村の行政職や福祉職等の公務員試験に合格して、福祉事務所、児童相談所等のケースワーカーなどに採用される場合に有効な資格です。
また、社会福祉主事は、児童相談所や身体障害者更生相談所など専門行政機関における相談援助職の基礎資格とされています。
(1)社会福祉主事の職務
社会福祉法の第18条3項および4項にあるように、都道府県の場合は、福祉に関する事務所(福祉事務所)において、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、市町村においては、それらに加えて、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うことを職務とします。
(2)社会福祉主事の資格の取得
社会福祉法の第19条1項1号に、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者」とあり、指定科目の中から3科目以上修得することにより資格を取得できます。
本学社会学部総合社会学科における開講科目は次のとおりです。
| 厚生労働大臣の指定する科目 | 本学開講科目 | |
|---|---|---|
| 社会福祉概論 | 【専攻科目】 | ①社会調査入門 ②社会福祉原論 |
| 社会福祉援助技術論 | 【専攻科目】 | ソーシャルワークの基盤と専門職及びソーシャルワークの基盤と専門職(専門)及びソーシャルワークの理論と方法及びソーシャルワークの理論と方法(専門)(要4科目履修) |
| 社会福祉調査論 | 【専攻科目】 | 社会福祉調査の基礎 |
| 社会福祉施設経営論 | 【専攻科目】 | 福祉サービスの組織と経営 |
| 社会保障 | 【専攻科目】 | 社会保障論 |
| 公的扶助論 | 【専攻科目】 | 貧困に対する支援 |
| 児童福祉論 | 【専攻科目】 | 児童福祉論 |
| 身体障害者福祉論 | 【専攻科目】 | 障害者福祉論 |
| 知的障害者福祉論 | 【専攻科目】 | 障害者福祉論 |
| 精神障害者保健福祉論 | 【専攻科目】 | 精神保健福祉の原理 |
| 老人福祉論 | 【専攻科目】 | 高齢者福祉論 |
| 地域福祉論 | 【専攻科目】 | 地域福祉論 |
| 法学 | 【専攻科目】 | 法学概論 |
| 経済学 | 【専攻科目】 | 経済原論 |
| 社会政策 | 【専攻科目】 | 労働と暮らしの社会政策 |
| 心理学 | 【教養科目】 | 心理学 |
| 【専攻科目】 | 心理学と心理的支援 | |
| 社会学 | 【専攻科目】 | 社会学概論 |
| 教育学 | 【教養科目】 | 教育原論A及び教育原論B(要2科目修得) |
| 倫理学 | 【教養科目】 | ①倫理学入門 ②倫理学A及び倫理学B(要2科目修得) |
| 医学一般 | 【専攻科目】 | 医学概論 |
※ 社会福祉主事資格は任用資格ですが、社会福祉施設・機関によっては求人の際の採用条件として社会福祉主事資格取得見込を条件としているところもあるので注意してください。
※ 「倫理学入門」「倫理学A」及び「倫理学B」の3科目を修得しても、厚生労働大臣の指定する科目を3科目修得したことはなりませんので、注意してください。
詳細は下記ホームページにて確認してください。
・厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」
(URL) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html
(QRコード)
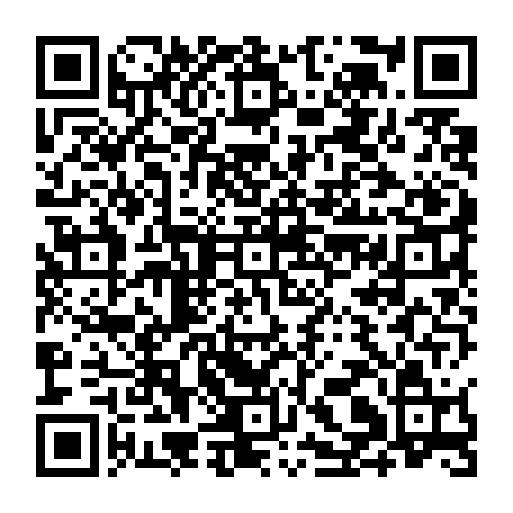
・本学履修要項WEBサイト
(URL)https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/
(QRコード)
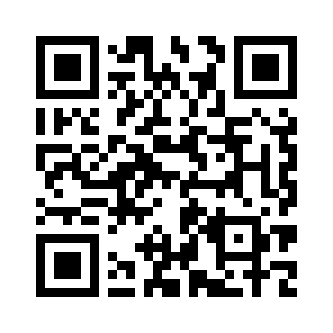
【5】児童指導員任用資格・児童の遊びを指導する者任用資格
児童福祉施設において直接児童と関わる職種をめざす場合に有効な資格として、「児童指導員任用資格」、「児童の遊びを指導する者」があります。「児童指導員」は児童養護施設等で、「児童の遊びを指導する者」は児童厚生施設で必置とされる職種です。法律の定めにより、これら職種に任用されるための条件があります。
1)児童指導員任用資格
- 児童指導員の職務
児童指導員とは、児童養護施設等において、児童の生活指導を行う者をいいます。 - 児童指導員の資格の取得
児童指導員の資格は、次のいずれかの条件を満たすことにより取得できます。
- 社会福祉士の資格を有する者。
- 精神保健福祉士の資格を有する者。
- 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者。本学社会学部はこれに該当します。
- 教育職員免許法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者で、都道府県知事が適当と認めたもの。
2)児童の遊びを指導する者任用資格
(1)児童の遊びを指導する者(児童厚生員)の職務
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第38条にあるように、児童館等の児童厚生施設において、児童の遊びを指導する者をいいます。
(2)児童の遊びを指導する者の資格の取得
児童の遊びを指導する者の資格は、次のいずれかの条件を満たすことにより取得できます。
- 保育士の資格を有する者。
- 社会福祉士の資格を有する者。
- 教育職員免許法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者。
- 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者で児童厚生施設の設置者が適当と認めたもの。本学社会学部はこれに該当します。
詳細は下記ホームページにて確認してください。
・本学履修要項WEBサイト
(URL)https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/
(QRコード)
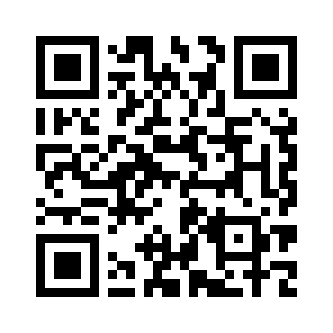
【6】諸課程
| 教職課程 | 担当窓口・関係情報 |
|---|---|
| 教職課程は、教員免許状の取得を目指す学生を対象とした課程です。教科等に関する確かな専門的知識はもちろん、広く豊かな教養、人間の成長・発達への深い理解、生徒に対する教育的愛情、教育者としての使命感を基盤とした、実践的な指導力を養成することを目的に設置しています。教職課程の履修にあたっては、「履修要項別冊 教職課程ガイドブック」を熟読してください。 また、教職センターでは、教職課程履修者を対象に教員採用試験突破のための基礎力・実践力養成講座なども実施しています。 |
(担当窓口) 教職センター 深草学舎 紫英館1階 大宮学舎 西黌1階 瀬田学舎 3号館1階 (関係情報)
|
| 本願寺派教師資格課程 | 担当窓口・関係情報 |
| 本願寺派教師資格課程は、浄土真宗本願寺派における寺院の住職や布教使になるために必要となる資格課程です。本学では、本願寺派教師資格に関する養成施設としての認定を受け、資格課程にかかわる科目を開設しており、1回生から受講することが可能です(受講する場合は、科目一覧を確認のうえ、履修登録をしてください)。 この課程は、最終的には浄土真宗本願寺派が実施する本資格に関連する試験・研修を受けなければなりません。 資格制度の詳細について、不明な点等がありましたら、浄土真宗本願寺派僧侶養成部に尋ねてください。 履修に関する詳細については、担当窓口に尋ねてください。 |
(担当窓口) 社会学部教務課 深草学舎紫英館1階 (関係情報)
|
| レクリエーション・インストラクター | 担当窓口・関係情報 |
| (財)日本レクリエーション協会の公認資格です。 余暇やレクリエーションに関する理論と実技を学び、レクリエーションを楽しく教える指導者として、地域を中心に社会福祉や企業等あらゆる領域で活動します。所定科目の単位を修得するとともに、日本レクリエーション協会等が関係する事業へ参加し卒業すると取得できます(協会への資格取得手続きが必要です)。 |
(担当窓口) 社会学部教務課 深草学舎紫英館1階 (関係情報)
|
| 健康教育専門士 | 担当窓口・関係情報 |
| 健康教育専門士とは「個々人の心身に応じた、安全で効果的な生活習慣改善活動を実施するためのプログラムの作成および指導を行う者」です。保健医療関係者、健康推進員など地域の人的資源と連携しつつ安全で効果的な生活習慣改善活動を実施するためのプログラム作成および実践を行います。特定健診・特定保健指導において、地域のポピュレーションアプローチを担い活躍できる人材として期待されます。 | (担当窓口) 社会学部教務課 深草学舎紫英館1階 (履修に関する情報)
|
【7】特別研修講座・各種講座・試験
| 課程・講座 | 目的・内容 | 担当部署 |
|---|---|---|
| 国際伝道者養成課程 | 広く国際的な素養として英語で仏教・浄土真宗を学修することや、海外の仏教事情に関心を持つ方を対象にした課程であり、また同時に、将来、浄土真宗本願寺派の海外開教区で伝道者として活躍できる人材養成を目的とした講座です。 | (深草/大宮)文学部教務課 |
| 矯正・保護課程 | 刑務所、少年院、少年鑑別所等で働く矯正職員や、犯罪をおかしたり非行を行った人たちの社会復帰を手助けする保護観察官等の専門職やボランティアを養成するために、実務に即した教育プログラムを提供しています。 | 矯正・保護総合センター 事務部 深草学舎 4号館2階 〈各学舎申し込み窓口〉 (深草) 法学部教務課 深草学舎 紫英館1階 (大宮) 文学部教務課 大宮学舎 西黌1階 |
| 法職課程 | 各種公務員試験(国家一般職、地方上級等)の合格や法科大学院進学を目指す学生に対し、法律科目を体系的かつ効率的に学習できる講座や最新の試験情報などを提供しています。また、法職カウンセラーが常駐し、学習方法や受験対策のアドバイスを行っています。 |
法学部教務課 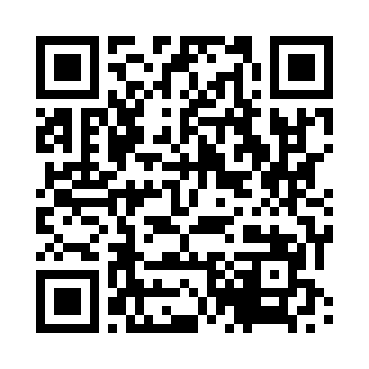 |
| キャリア支援講座 ※受講希望者が少ない場合、開講できないことがあります。 ※開講する学舎が限定されている講座があります。 |
キャリアアップに向けた資格取得や公務員試験などの対策が必須の就職を支援するために、各種講座を開講しています。資格取得等に信頼と実績のある有名予備校等と提携し、一人ひとりの目標や夢の実現をバックアップします。 〈資格系〉 宅地建物取引士講座/旅行業務取扱管理者講座/社会福祉士国家試験講座 〈語学系〉 TOEIC®Listening&ReadingTest対策講座 〈就職対策〉 公務員講座/エアライン就職対策講座 |
キャリアセンター 深草学舎 5号館1階 大宮学舎 東黌2階 瀬田学舎 1号館1階 |
| 社会福祉士国家試験講座(キャリア支援講座) | 社会福祉士受験資格科目を体系的に理解して、社会福祉士国家試験合格を目指します。高い合格率を誇っています。 |
キャリアセンター |
| 手話講座 | 社会福祉法人全国手話研修センターとの連携事業により、「手話コミュニケーションコース」「手話ステップアップコース」「手話通訳コース」を実施します。「手話コミュニケーションコース」では全国手話検定試験2級レベルを、「手話ステップアップコース」では全国手話検定試験1級レベルを目指し、「手話通訳コース」では手話通訳者全国統一試験に備える力を養います。 |
REC事務部 社会福祉法人全国手話 研修センターホームページ 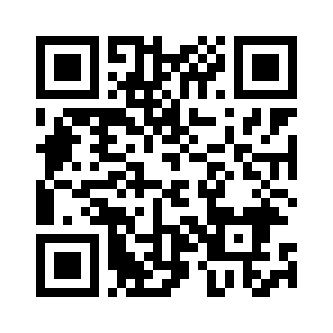 |
 検索
検索