Need Help?
研究助成・博士後期課程対象奨学金・規程等
最終更新日: 2025年1月30日
研究助成について
大学院生の研究環境の向上を図るため、以下の独自の研究助成制度を設けています。但し、休学中の学生は除きます。
1.修士課程
- 大学院生研究援助費(年1回申請)
申請にもとづき、6,000円(上限)/年度の図書購入費、文献複写料を支給します。 - 学会発表援助費(年3回<上限>)
教員の申請にもとづき、10,000円(1回当たりの上限額)×3回/年度を学生の学会発表援助費として支給します。 - 理工学会「学生会員の研究・開発活動に対する補助」
申請にもとづき、50,000円(上限)/年度の学会発表などにかかる旅費等を支給します。
ただし、補助対象活動ごとに補助対象となる項目や上限金額等が異なりますので、詳細は理工学会HPをご確認ください。
<窓口:理工学会事務局1号館1階研究部(瀬田)内>
(URL)https://www.rikou.ryukoku.ac.jp/gakkai/
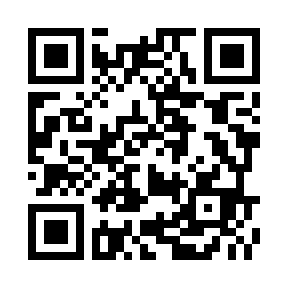
2.博士後期課程
- 先端理工実験実習費研究助成
申請にもとづき、200,000円(上限)/年度の研究助成金を支給します。各自の研究活動にかかる旅費、学会参加費等に充当できます。 - 大学院生研究援助費(年1回申請)
申請にもとづき、6,000円(上限)/年度の図書購入費、文献複写料を支給します。 - 学会発表援助費(年3回<上限>)
教員の申請にもとづき、10,000円(1回当たりの上限額)×3回/年度を学生の学会発表援助費として支給します。 - 理工学会「学生会員の研究・開発活動に対する補助」
申請にもとづき、50,000円(上限)/年度の学会発表などにかかる旅費等を支給します。
ただし、補助対象活動ごとに補助対象となる項目や上限金額等が異なりますので、詳細は理工学会HPをご確認ください。
<窓口:理工学会事務局1号館1階研究部(瀬田)内>
(URL)https://www.rikou.ryukoku.ac.jp/gakkai/
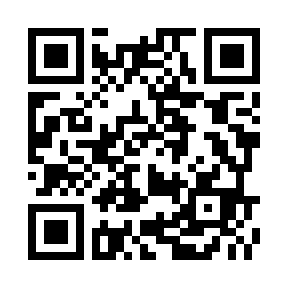
先端理工学研究科博士後期課程へ進学する学生が対象となる給付奨学金制度について
- 内容に変更が生じる場合がありますので、本給付奨学金制度の詳しい内容については、当該年度の「奨学金ガイドブック」で必ずご確認ください。
1.大学院学内進学奨励給付奨学金(予約採用型)<自己応募>
本学大学院先端理工学研究科博士後期課程への進学を奨励するため、本学大学院修士課程から進学した者を対象に、給付する奨学金です。
- <申請時期・方法>
「大学院先端理工学研究科博士後期課程一般入学試験」の入学試験の出願期間(※)に所定の申請書を提出
※出願期間は、入試要項でご確認ください。 - <採用人数>
別途ポータルサイトにて周知 - <給付額(予定)>
150,000円(入学年度のみ)
2.大学院研究活動支援給付奨学金<自己応募>
本学大学院先端理工学研究科博士後期課程に在学し、学業成績および人物が優秀で、かつ研究活動での財政的支援が必要である者を対象に給付する奨学金です。
- <申請時期・方法>
所定の期日までに申請書を先端理工学部教務課へ提出(別途ポータルサイトにて周知) - <採用人数>
別途ポータルサイトにて周知 - <給付額(予定)>
150,000円(採用された年度のみ)
3.大学院成績優秀者給付奨学金<推薦制>
本学大学院先端理工学研究科博士後期課程2・3年次生のうち、学業成績および人物が特に優秀な者を対象に給付する奨学金です。
- <奨学生決定連絡>
対象者に個別に連絡します。※自己応募制ではありません。 - <給付額(予定)>
150,000円(採用された年度のみ)
4.先端理工学研究科博士後期課程特別給付奨学金<推薦制>
本学大学院先端理工学研究科博士後期課程において優秀な学生を確保することを目的に、入学試験の成績優秀者に対して給付する奨学金です。
- <給付額(予定)>
290,000円 - <給付期間>
3年間(毎年度、学業成績審査あり)
規程等
龍谷大学大学院先端理工学研究科研究指導要項
龍谷大学大学院先端理工学研究科の教育は、授業および学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という)によって行うものであるが、本要項は、研究指導の大綱を規定するものである。授業科目については、龍谷大学大学院学則の規定するところによる。
1.修士課程における研究指導
(1)研究題目・指導教員の選定
ア.各コース学生は、入学後すみやかに、研究題目を決め、その題目に応じて、指導教員1名(以下、「指導教員(主)」という)を選ばねばならない。
なお、必要に応じて指導教員(副)を選ぶことができる。
イ.指導教員(主)は、原則として、当該コースの先端理工学研究科修士課程特別研究担当の専任教員でなければならない。
指導教員(副)は、原則として、先端理工学研究科修士課程の講義担当の専任教員のうちから指導教員(主)の同意を得て、選ばねばならない。
ウ.指導教員(主)が、特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、他研究科の専任教員を指導教員(副)として選ぶことができる。
(2)研究題目届・指導教員選定届
ア.研究題目届・指導教員選定届については、所定の用紙に指導教員(主)の認印を得て、入学年次の所定の期日までにその届出を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。
イ.やむを得ず研究題目等の変更の必要がある場合には、指導教員(主)の同意を得た上、所定の用紙に必要事項を記入し、研究科委員会の承認を得なければならない。
(3)修士論文
ア.指導教員(主)の指導を受けて、修士論文審査願を、所定の期日までに提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。
イ.論文作成の指導ないし助言は、指導教員から受けるものとする。
2.博士後期課程における研究指導
(1)研究題目・指導教員の選定
ア.各コース学生は、研究題目に応じて、指導教員1名(以下、「指導教員(主)」という)を選ばねばならない。なお、必要に応じて指導教員(副)を選ぶことができる。
イ.指導教員(主)は、原則として、当該コースの先端理工学研究科博士後期課程特別研究担当の専任教員でなければならない。
指導教員(副)は、原則として、先端理工学研究科博士後期課程の講義担当の専任教員のうちから指導教員(主)の同意を得て、選ばねばならない。
ウ.指導教員(主)が、特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、他研究科の専任教員を指導教員(副)として選ぶことができる。
(2)研究題目届・指導教員選定届
ア.研究題目届・指導教員選定届については、所定の用紙に指導教員(主)の認印を得て、所定の期日までにその届出を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。
イ.やむを得ず研究題目等の変更の必要がある場合には、指導教員(主)の同意を得た上、所定の用紙に必要事項を記入し、研究科委員会の承認を得なければならない。
(3)博士論文
ア.指導教員(主)の指導を受けて、研究の内容、方法などの大綱を記述した博士論文概要および博士論文審査願を、所定の期日までに提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。
イ.博士論文は、指導教員(主)の指導とその同意のもとに作成するものとする。
龍谷大学大学院先端理工学研究科学位論文審査等規程
第1章 修士論文の審査等
(論文の提出資格)
第1条 龍谷大学大学院先端理工学研究科の修士課程学生で、その所属するコース所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位以上をその学年度までに取得した者、または取得見込みの者は、所定の手続により所定の期日までに修士論文の審査願を提出の上、修士論文を提出できる。
(論文の受理)
第2条 前条の規程を満たし提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するものでなければならない。
2.提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。
(論文の審査)
第3条 修士論文の審査は、修士論文提出者の所属する各コースごとに、修士課程の特別研究担当の研究科専任教員を含む2名以上の審査員によって行われる。
2.修士論文の審査には、口述試験を課する。
(論文の合否)
第4条 修士論文は、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。
2.修士論文は、社会の要請する学術的あるいは科学技術的課題に対し、当該分野の高度な専門知識および関連分野の幅広い基礎知識を駆使し、与えられた条件の下で、その課題を分析し、解決に至る手順を示し、それを実行し、その結果を明瞭に表現したものであること。
3.修士論文の合否は、論文の内容ならびに口述試験の結果によって判定する。
第2章 博士論文の審査等
(規程の対象)
第5条 龍谷大学大学院先端理工学研究科の行う博士論文の審査は、龍谷大学大学院学則の定める博士課程修了の要件の一つとして行われるものと、龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるものの2種類あるが、本規程は、前者にかかわる審査等の大綱を規定するものである。後者にかかわる審査等については、本学学位規程によるものとする。
(論文の提出資格)
第6条 龍谷大学大学院先端理工学研究科の博士後期課程学生で、その所属するコース所定の博士後期課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な14単位以上をその学年度までに取得した者、または取得見込の者は、所定の手続により所定の期日までに博士論文の審査願を提出の上、博士論文を提出できる。
(論文の受理)
第7条 前条により博士論文を提出する者は、論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、本学学位規程付載の別表第7の様式による履歴書、各3通を提出するとともに、所定の審査手数料を納付するものとする。
2.提出された博士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。
(論文の審査)
第8条 本研究科委員会は、博士論文の審査に当たり、必要があるときは、論文の提出者に対して、当該論文の関係論文、訳本その他の提出を求めることができる。
第9条 本研究科委員会は、論文提出者の所属するコースの博士後期課程授業科目の担当教授および関連のある研究科授業科目担当教授のうちから3名以上の審査員を選び、その審査に当たらせる。
2.本研究科委員会が必要と認めるときは、前項の規程にかかわらず、本研究科の授業担当の准教授、講師を審査員に入れることができる。
3.本研究科委員会が必要と認めるときは、本条第1項の規程にかかわらず、龍谷大学大学院他研究科および他大学の大学院等の教員等を審査員に入れることができる。
第10条 博士論文の審査には、口述試験を課する。
2.前項の口述試験は、当該論文の審査員および本研究科委員会で承認された他の委員を含む5名が担当し、本研究科の授業担当の教員は、その試験に陪席することができる。
(論文の合否)
第11条 博士論文は、その専攻分野について、研究者・技術者として自立して研究・開発活動を行うに必要な高度の研究・開発能力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足りるものでなければならない。
第12条 本研究科委員会は、審査員より当該論文の審査報告を受け、論文の合否を決定する。
付則
第1条 この規程は、龍谷大学大学院理工学研究科内規として、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月8日第1章改正第2章新設)
第1条 この規程は、龍谷大学大学院理工学研究科内規として、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月17日第2章第6条第2項一部改正)
第1条 この規程は、龍谷大学大学院理工学研究科内規として、平成9年4月1日から施行し、平成9年度博士後期課程入学者から適用する。ただし、平成8年度以前博士後期課程入学者については、なお従前の規程を適用する。
付則(平成31年2月9日第2章第6条第2項削除)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学生については、なお従前の規定による。
付則(令和6年1月24日第1章第1条、第3条、第2章第5条、第6条、第9条改正)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学生については、なお従前の規定による。
龍谷大学大学院先端理工学研究科学生の学部科目履修に関する内規
(資格)
第1条 龍谷大学大学院先端理工学研究科に在籍し、先端理工学部開講授業科目の履修を志願する者の取扱いはこの規程による。
(出願手順)
第2条 学部科目の履修を志願する者は、所定の願書に受講希望科目を記入し、先端理工学部教務課を経て先端理工学研究科長に提出する。
(対象外科目)
第3条 先端理工学部では、「セミナー」、「英語総合1(A)・1(B)・2(A)・2(B)・3・4」、および英語以外の外国語は履修できない。
2.前項以外の科目でも実験・実習、演習あるいは講義の性格上履修を認められない場合もある。
(許可)
第4条 先端理工学研究科長は前条の願書を受付けたときは、先端理工学研究科委員会の議にもとづき、先端理工学部教授会の承認を経て、これを科目等履修生として許可する。
(学費等)
第5条 履修料等学費は1単位につき7,500円とし、単位の計算方法は学則に準ずる。(受講料は龍谷大学科目等履修生要項に準ずる)
なお、無料とする科目は別表1のとおりとし、他は全て有料とする。
(教育実習及び介護等体験)
第6条 教職専門科目「介護等体験」「教育実習指導ⅡA」「教育実習指導ⅡB」の履修は龍谷大学科目等履修生出願要項に準ずる。(教育実習費及び介護等体験に係る費用については別途納入するものとする。)
(単位認定・証明書発行)
第7条 履修科目の試験に合格した者には、その所定の単位を与え、願い出により証明書を発行する。
(諸課程)
第8条 本願寺派教師資格等の課程については、それぞれの必修科目のみ無料とする。
別表1)
- 修了の条件として在学中に単位取得するよう指定した科目。
- 教員免許状取得に係る科目の内、教職に関する科目。
- 教員免許状取得に係る科目の内、専修免許状取得に必要な教科に関する科目。
なお、コースごとに取得できる専修免許状は次のとおりである。
数理・情報科学コース(数学)、知能情報メディアコース(情報)、電子情報通信コース(工業)、機械工学・ロボティクスコース(工業)、応用化学コース(理科)、環境科学コース(理科)
付則
第1条 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年1月31日改正)
第1条 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月16日第3条・第6条一部改正)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日第1条、第2条、第3条、第4条、第6条改正)
第1条 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 令和元年度以前の入学生については、なお従前の規定による。
付則(令和6年1月24日第1条,第2条,第4条,別表1)改正)
第1条 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 平成5年度以前の入学生については、なお従前の規定による。
教職課程履修料の納入に関する要領
(目的)
第1条 この要領は、龍谷大学学則第22条第2項並びに学費等納入規程第7条の2及び第17条の2に基づき、教職課程履修料(以下「履修料」という。)の納入について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 教職課程に登録する者は、履修料を納入しなければならない。
(履修料の納入)
第3条 履修料を納入する者は、学費等納入規程別表4の2に定める履修料30,000円を3年度間に分割し、2年次生から1年度当たり10,000円ずつ納入する。
2 前項の規定にかかわらず、教職課程に3年次生から登録する者は、3年次生に20,000円を納入し、4年次生に10,000円を納入する。
3 前2項の規定にかかわらず、教職課程に4年次生以降に登録する者は、登録を開始する年度に30,000円を一括で納入する。
4 一旦納入された履修料は、履修辞退を含むいかなる理由があっても返還しない。
5 次の各号の一に該当する者は、当該年度の履修料の納入は必要としない。
- 休学又は留学している者
- 進級制度をとる学部において同一年次に複数年度にわたり在籍する者
- 教職課程への登録を中断する者
(納入時期)
第4条 履修料は、教職センターが定める期間に納入することとする。
(履修料の取扱い)
第5条 履修料を一旦納入した者が教職課程への登録を中断し、改めて登録を再開する場合は、過去に納入した履修料を除いた当該学年までの履修料を一括で納入することとする。
(大学院生及び科目等履修生の取扱い)
第6条 大学院生及び科目等履修生が、教職課程に登録する場合、次の各号のいずれかに基づき取り扱うものとする。
- 過去に履修料を納入していない者は、教職課程に登録する年度に履修料を一括して納入する。
- 過去に履修料を納入している者は、過去に納入した履修料を除いた履修料を一括で納入する。
- 大学院において専修免許状のみの課程を履修する場合、履修料の納入は必要としない。
(要領の改廃)
第7条 この要領の改廃は、教職センター会議の議を経て部局長会において決定する。
付則
1 この要領は、制定日(平成30年7月26日)から施行する。
2 この要領は、平成30年度入学の学部生から適用する。
3 編入学生及び転入学生へのこの要領の適用は、平成32年度入学の編入学生及び転入学生からとする。
4 大学院生及び科目等履修生へのこの要領の適用は、平成30年度入学の学部生が学部を卒業し、大学院生及び科目等履修生となる平成34年度からとする。ただし、大学院生及び科目等履修生が、学部在籍時に「龍谷大学学則第32条関係別表4」に定める科目を履修していない場合には、平成31年度以降入学の大学院生及び平成31年度以降の科目等履修生に対し、この要領を適用する。
付則(令和5年1月12日第4条,第5条改正)
この要領は、制定日(令和5年1月12日)から施行する。
特別専攻生規程
(設置)
第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。
(対象と目的)
第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院先端理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院先端理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院先端理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。
(出願)
第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。
(期間)
第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。
(研修費)
第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院先端理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。
(待遇)
第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
- 担当教員の指導を受けること。
- 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。
(身分証明書)
第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。
(準用)
第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。
付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。
※出願方法等については、ポータルサイト及び大学院先端理工学研究科掲示板にて周知する。(2月及び9月上旬頃)
研究生要項
研究生の取り扱いは、下記の大学院学則第9章の2研究生の項による。
第9章の2 研究生及び特別専攻生
第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。
第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願出なければならない。
2.研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。
第36条の4 研究生の期間は、1学年間又は1学期間とする。
2.研究の継続を希望する者は、期間の更新を願出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。
第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。ただし、先端理工学研究科については、年額3万円とする。
2.1学期間在籍の場合、研修費については、前項に定める年額の2分の1の金額を納入する。
第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
- 教授の指導を受けること。
- 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。
- 大学院学生の研究を妨げない範囲で、特定の科目を聴講すること。
第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。
第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。
※出願方法等については、ポータルサイト及び大学院先端理工学研究科掲示板にて周知する。(2月及び9月上旬頃)
 検索
検索